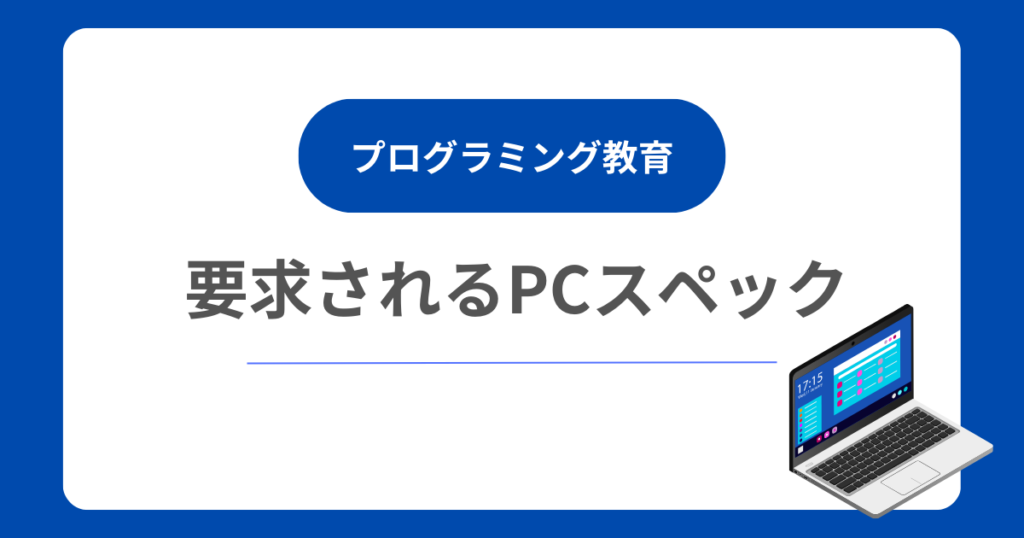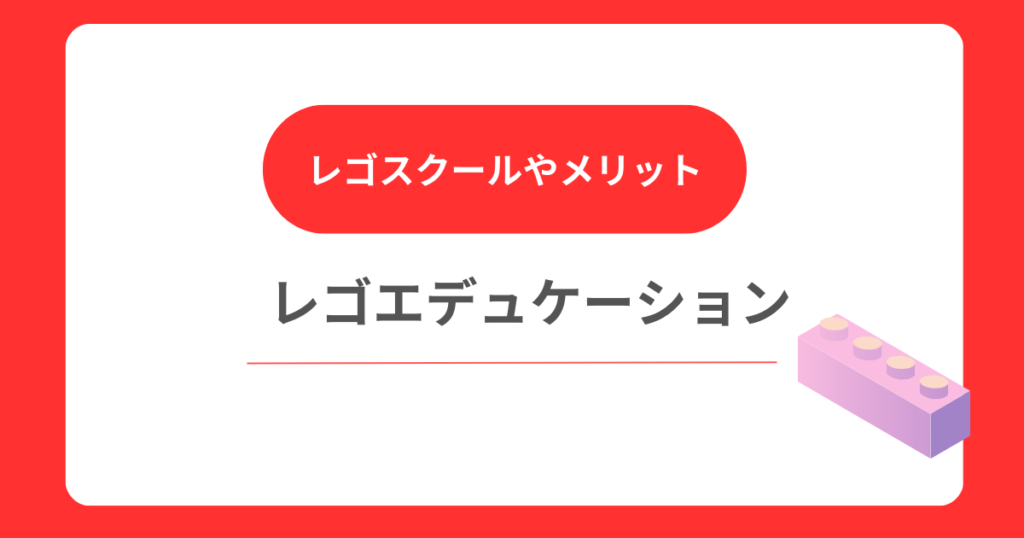ワクワクする仕掛けをレゴで再現!

「ピタゴラスイッチ」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは、NHKの教育番組でおなじみの、あの不思議な連鎖装置。
ビー玉が転がり、ドミノが倒れ、最後にちょっとしたサプライズが起きる──そんな仕掛けを見ていると、大人でも思わず「おお!」と声をあげてしまいますよね。
今回は、そんなピタゴラスイッチのような連鎖装置を、レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライムで作った作品をご紹介します。
SPIKE™はもともとプログラミング教育用に開発された学習キットですが、実は遊び心あふれる作品づくりにも最適。
レゴブロックの自由度と、モーターやセンサーなどの電子要素を組み合わせることで、まるで生きているような動きを作り出すことができます。
この記事では、
- 作品のコンセプト
- 仕掛けの構造
- プログラミングやデザインの工夫
- 実際に遊んでみた感想
を順に紹介していきます。
「ピタゴラスイッチって作れるの?」と気になっている方にも、ぜひ参考にしていただける内容です。
作品のコンセプト

今回のテーマは「動き出したら止まらない仕掛け」。
ビー玉やボールを転がすだけでなく、モーターやセンサーの制御を組み合わせて、アナログとデジタルが融合した連鎖反応を目指しました。
具体的には、
- スタートのスイッチを押す
- モーターが回転してボールを発射
- ボールが坂道を転がり、ドミノを倒す
- ドミノの最後がカラーセンサーの前に赤いブロックを置く
- センサーが反応して、別のモーターが動き出す
- アームが持ち上がり、次のボールを転がす
という流れで進みます。
単純に見えて、複数の仕掛けが組み合わさっているので、成功したときの達成感は抜群です。
仕掛けの詳細

① スタートボタン
SPIKEのハブ本体についているボタンをスタートスイッチに設定。
押すとプログラムが始まり、最初のモーターが動き出します。
② ボール発射装置
中型モーターを使い、レバー式の発射装置を作成しました。
レバーを後ろに引き、モーターが勢いよく回転すると、ビー玉がコースに飛び出します。
この「最初の一押し」があると、一気に物語が始まった感じがしてワクワクします。
③ 坂道+ドミノコース
ビー玉が坂道を転がり、並べられたドミノを倒していきます。
レゴブロックで坂道をつくるのは少し大変でしたが、プレートとテクニックパーツを組み合わせて、なめらかに転がる傾斜を調整しました。
ビー玉の勢いが足りないと途中で止まってしまうので、角度の微調整がポイントです。
④カラーセンサーによる反応
ドミノの最後に赤いブロックを置き、そのブロックがカラーセンサーの前に倒れる仕組みを組み込みました。
センサーが赤を検知すると、プログラムが次の動作に移ります。
ここで「アナログの倒れる動き」と「デジタルのセンサー検知」がつながる瞬間が見どころです。
⑤アームの動作
センサーが反応したら、大型モーターが動き出し、アームがぐいっと持ち上がります。
その上に置いていたビー玉が転がり、次の仕掛けへとバトンタッチ。
このときの「持ち上がった瞬間の間」が、ピタゴラスイッチらしいユーモラスな動きを演出しています。
⑥ フィナーレ
最後はビー玉がゴールのカップにストンと落ち、LEDライトが点灯して終了。
小さなゴールですが、光が加わると「やり遂げた!」という雰囲気になります。
工夫したポイント

- プログラムはシンプルに
SPIKEは複雑なプログラミングもできますが、あえて「モーターを回す」「センサーが反応したら次へ」といった基本動作を組み合わせるだけにしました。
これにより、誰でも真似しやすく、改造も自由になります。 - アナログとデジタルの融合
ただプログラム通りに動くだけでは、ロボット工作に近くなってしまいます。
今回は「ビー玉が転がる」「ドミノが倒れる」といった物理的な仕掛けと「センサー検知」をミックスさせることで、ピタゴラスイッチらしい予測不能の楽しさを再現しました。 - 見た目の面白さ
装置の途中に小さな人形を置いたり、カラフルなブロックで装飾したりと、ただ機能するだけでなく「眺めて楽しい」作品に仕上げました。
動作中に人形が巻き込まれるような演出は、子どもたちにも大ウケでした。
実際に遊んでみた感想

作ってみて一番感じたのは、「うまくいかない時間も楽しい」ということです。
ビー玉が途中で止まったり、センサーが反応しなかったり、何度も失敗しましたが、そのたびに「どこを直せばいいか?」を考える過程がとても面白い。
子どもと一緒に取り組むと、自然に「試行錯誤する力」が育まれるのを実感しました。
また、親子で協力して作ったのですが、子どもは「装飾担当」、親は「仕掛け担当」と役割分担して進めました。
完成後に一緒にスイッチを押して、仕掛けが最後まで成功した瞬間、思わず二人で拍手してしまいました。
まさに共同作業の喜びを感じられる体験です。
まとめ
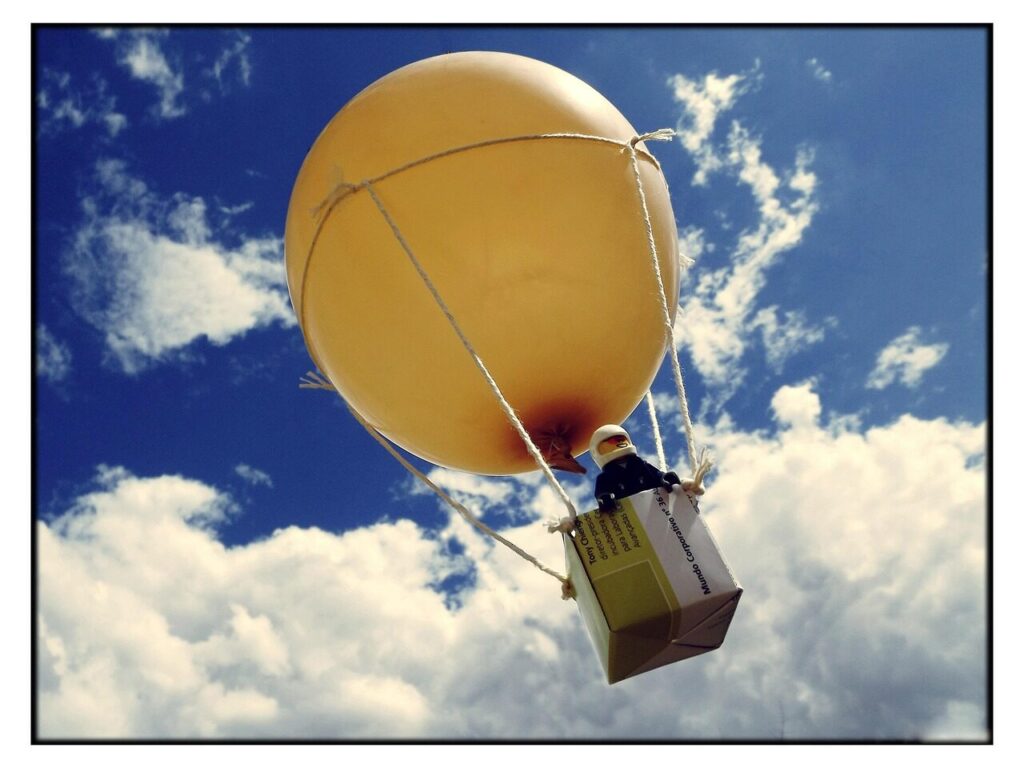
Lego Balloon Toy – Free photo on Pixabayより引用
レゴ®SPIKE™を使ったピタゴラスイッチ風作品は、単なる「プログラミング教材」の枠を超えた遊び心に満ちています。
- レゴの拡張性
- センサーやモーターの組み合わせ
- ピタゴラスイッチ的な発想
この三つが合わさることで、オリジナルの連鎖装置が自由自在に作れます。
「子どもと一緒に楽しむ工作」としてもおすすめなため、もしSPIKEをお持ちなら、ぜひ一度ピタゴラスイッチづくりに挑戦してみてください。
失敗も成功も含めて、必ず忘れられない体験になるはずです。