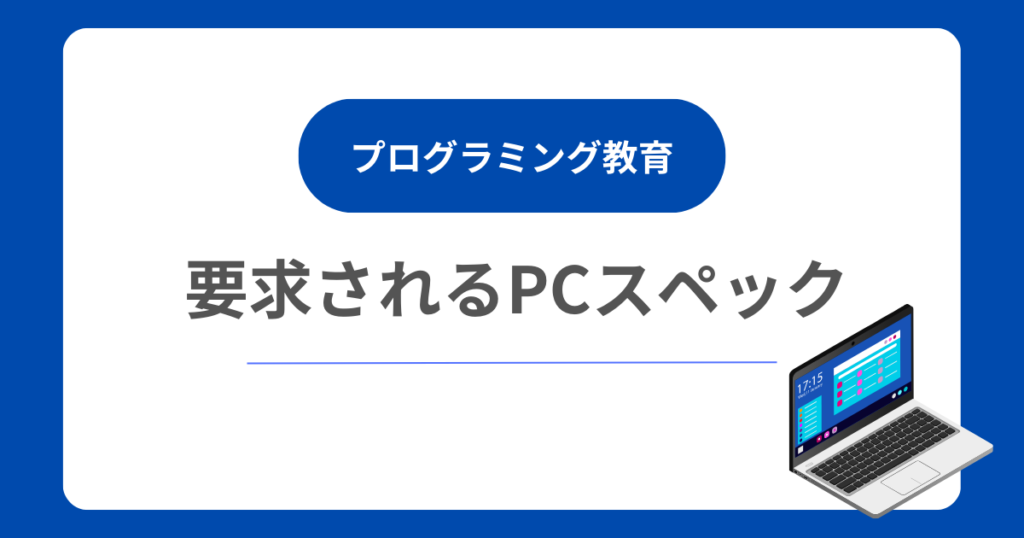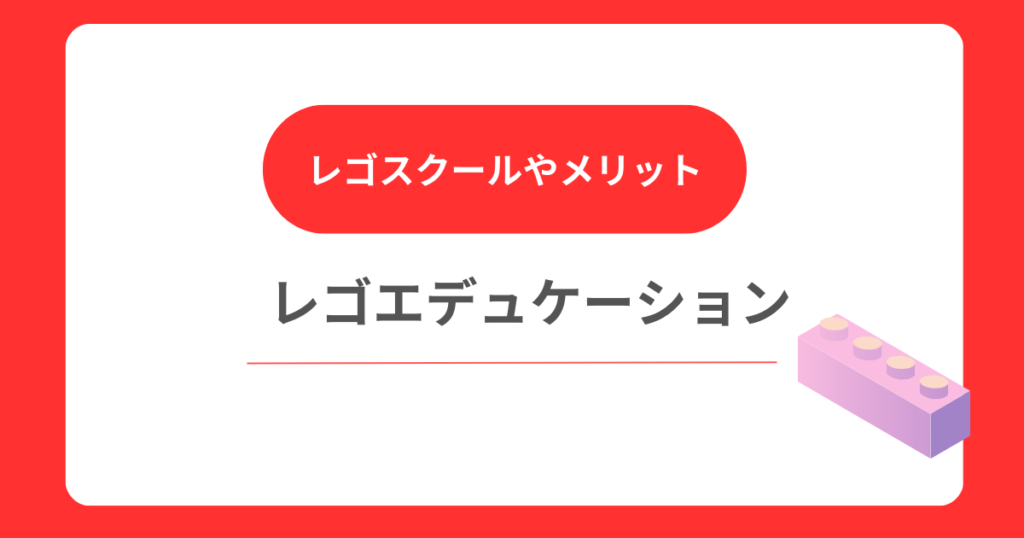「これからの時代、どんな力を育てればいいの?」教育の転換期に立つ保護者へ
「AIが発達したら、今の仕事の半分はなくなる」
そんなニュースを見るたびに、「うちの子が大人になる頃、どんな力が必要なんだろう」と不安に感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。
実は今、日本の教育は大きな転換期を迎えています。
文部科学省が推進する新しい学習指導要領では、「知識を覚える」教育から「自ら考え、行動する」教育へと、学びのあり方が根本から変わろうとしています。
そのキーワードが「21世紀型スキル」と「アクティブラーニング」。
今回は、なぜレゴスクールがこれからの時代に必要な力を育てるのか、25年の実績を持つSCCIPの教育アプローチとともに解説します。
「21世紀型スキル」とは?なぜ今、注目されているのか
暗記だけでは生き抜けない時代がやってくる
少し前まで、「良い成績を取る=知識をたくさん覚える」ことでした。
しかし、インターネットで検索すれば瞬時に答えが見つかる今、単なる知識の暗記だけでは、AIやテクノロジーに代替されてしまう可能性があります。
これからの時代に必要なのは、**知識を「使いこなす力」**です。
世界が注目する「21世紀型スキル」の4つの柱
21世紀型スキルとは、国際団体ATC21sが提唱した、これからの社会で生き抜くために必要な能力のことです。
具体的には、以下の4つの力(4C)が重要とされています:
1. Critical Thinking(批判的思考力)
情報を鵜呑みにせず、「本当にそうなのか?」と疑問を持ち、自分で考え判断する力
2. Creativity(創造性)
正解が一つではない問題に対して、新しい解決策やアイデアを生み出す力
3. Communication(コミュニケーション能力)
自分の考えを的確に伝え、相手の意見も理解しながら対話する力
4. Collaboration(協働する力)
多様な人々と協力しながら、共通の目標を達成する力
この4つの力は、どんな職業に就いても、どんな困難に直面しても、人生を豊かにする「一生モノのスキル」なのです。
アクティブラーニングが子どもを変える理由
「教わる」から「学び取る」への大転換
もう一つの重要なキーワードが「アクティブラーニング(能動的学習)」です。
従来の教育は、先生が話す内容を生徒が聞いて覚える「受動的な学び」が中心でした。
しかし、アクティブラーニングでは:
- 子ども自身が問いを立てる
- 試行錯誤しながら答えを探す
- 仲間と議論し、協力する
- 学んだことを発表し、振り返る
このように、子どもが主体的に学びに関わることで、知識が定着するだけでなく、思考力や表現力が大きく伸びることが分かっています。
研究で証明された「アクティブラーニング」の効果
アメリカの教育学者エドガー・デールが提唱した「ラーニングピラミッド」によると:
- 講義を聞く:学習定着率5%
- 読書:10%
- 視聴覚教材:20%
- 実演を見る:30%
- 議論する:50%
- 実践・体験する:75%
- 他者に教える:90%
つまり、受動的に聞いているだけでは、学んだことの95%は忘れてしまうのです。
一方、自分で考え、手を動かし、人に説明する「能動的な学び」では、学習内容が深く定着します。
レゴスクールがアクティブラーニングの理想形である理由
実は、レゴを使った学びは、アクティブラーニングの理想的な形と言えます。
レゴ教育における「能動的学び」のサイクル
SCCIPのレゴ教室では、毎回の授業で以下のサイクルを回します:
1. 問いかけ(Question)
「この橋を渡れる車を作るには?」といったテーマが提示される
2. 探究・制作(Explore & Create)
子ども自身が考え、試行錯誤しながらブロックで作品を作る
3. 共有・議論(Share & Discuss)
作った作品を発表し、友達と意見交換する
4. 振り返り(Reflect)
「どこを工夫したか」「次はどうしたいか」を言語化する
この一連の流れは、まさにアクティブラーニングそのものです。
なぜレゴは「手を動かす学び」に最適なのか
レゴブロックの素晴らしさは、「考えたこと」をすぐに「形」にできることです。
頭の中のアイデアを、プログラミングコードや複雑な設計図なしに、直感的に表現できます。
そして、作ったものが思い通りに動かなければ、すぐに分解して作り直せる。
この「高速でPDCAを回せる環境」が、子どもの思考力と創造力を飛躍的に伸ばすのです。
プログラミング教室も素晴らしい。でも、21世紀型スキル育成には違いがある
近年、プログラミング教室やロボット教室など、STEM教育を掲げる習い事が増えています。これらの教室も、論理的思考力や問題解決能力を育てる素晴らしい学びの場です。
多くのプログラミングスクールが質の高いカリキュラムを提供しており、特に小学校高学年以降のお子さまにとって、将来のキャリアにつながる貴重な経験となるでしょう。
レゴ教育との決定的な違い:「創造性」と「コミュニケーション」のバランス
ただ、プログラミング教室の多くは、「コードを書く」「正しく動かす」という技術習得に重きが置かれる傾向があります。
一方、レゴを使った学びでは:
創造性(Creativity)の育成
- 正解は一つではない
- 同じテーマでも、子どもの数だけ異なる作品が生まれる
- 「こうしたい」という思いを形にする自由がある
コミュニケーション(Communication)の重視
- 毎回、作品を発表する時間がある
- 「なぜそう作ったのか」を言語化する
- 友達の作品を見て、新しい発見をする
つまり、21世紀型スキルの4Cすべてをバランスよく育てられるのが、レゴ教育の最大の強みなのです。
SCCIPが25年間追求してきた「アクティブラーニング×レゴ」
株式会社SCCIP JAPANは、2000年に日本で最初のレゴを使った教育を導入した、日本で最も伝統のあるレゴ教室です。
プログラミングスクールとは一線を画す教育哲学
「なぜSCCIPはプログラミングスクールにならないのですか?」
このご質問をいただくことがあります。
答えは明確です。私たちは、技術者を育てる前に、まず「考える人」を育てたいからです。
SCCIPでは、レゴ社の教育理念「子ども達の自発的な学びは、遊びから生まれる」を25年間貫いてきました。
プログラミングも学びますが、それは「課題を解決する一つの手段」であり、目的ではありません。
大切なのは:
- 自分で問いを立てる力
- 試行錯誤を楽しむ姿勢
- 失敗から学ぶ経験
- 自分の考えを人に伝える力
これらの土台があってこそ、どんな技術も活きてくるのです。
埼玉大学との連携が生む、科学的根拠のあるカリキュラム
SCCIPのカリキュラムは、埼玉大学STEM教育研究センターとの連携のもと開発されています。
「アクティブラーニングの効果」を科学的に検証しながら、常にカリキュラムをアップデート。
この25年間で蓄積したノウハウは、日本国内だけでなく、インド、フィリピン、タイ、スリランカなどアジア各国で3万人以上の子どもたちに届けられています。
グローバルな教育実践から得られた知見が、SCCIPの教育の質を支えています。
SCCIPのレゴ教室で育つ「21世紀型スキル」の具体例
Critical Thinking(批判的思考力)
授業での場面:
「この橋が壊れてしまうのはなぜ?」という問いに対して、子どもたちは自分で原因を探ります。
「ブロックの数が少ないから?」「バランスが悪いから?」と仮説を立て、一つずつ検証していく。
この経験が、物事を多角的に考える力を育てます。
Creativity(創造性)
授業での場面:
「動物園を作ろう」というテーマでも、正解は一つではありません。
ライオンの檻を作る子、観覧車を作る子、チケット売り場を作る子…子どもの数だけアイデアが生まれます。
「正解探し」ではなく「自分なりの答え作り」が、創造性を育てます。
Communication(コミュニケーション能力)
授業での場面:
毎回の発表タイムで、「どこを工夫したか」「どんな仕組みにしたか」を説明します。
最初は「かっこいいから」だった説明が、「ここをこうすると強くなるから」と理由を添えられるようになる。
この積み重ねが、論理的に説明する力につながります。
Collaboration(協働する力)
授業での場面:
「チームで一つの街を作ろう」というプロジェクトでは、役割分担や意見の調整が必要になります。
「僕は道路を作る」「私はお店を作るね」と協力しながら、一つの目標を達成する経験。
これが、将来あらゆる場面で活きる「チームワーク」の土台になります。
年齢別:21世紀型スキルの育ち方
SCCIPでは、年齢に応じて段階的に21世紀型スキルを育てます。
年少〜年中(ハローダクタコース)
- 「できた!」という達成感を積む
- 色や形の違いを言葉にする(コミュニケーションの芽生え)
- 友達と一緒に作る楽しさを知る(協働の芽生え)
年中〜小学校低学年(ダクタキッズコース)
- 「なぜ動くのか?」と疑問を持つ(批判的思考の芽生え)
- 自分なりの工夫を加える(創造性の発揮)
- 作品を説明する力が育つ
小学校低学年〜(ジュニアロボティクス・ロボティクスコース)
- 複雑な問題を分析し、解決策を考える
- プログラミングで論理的思考を強化
- チームで協力して高度な課題に挑戦
- プレゼンテーション能力の本格的育成
どの年齢から始めても、その子に合ったレベルで21世紀型スキルが育ちます。
保護者の方からよくいただくご質問
Q. 学校の成績は上がりますか?
A. SCCIPは受験対策の教室ではありませんが、「自分で考える力」「問題解決能力」が育つことで、学校の勉強への取り組み方が変わったというお声をよくいただきます。特に、理科や算数の理解が深まるケースが多いです。
Q. プログラミング教室と迷っているのですが…
A. プログラミング教室も素晴らしい選択肢です。ただ、お子さまが「コードを書くこと」に興味があるなら、小学校高学年以降からでも十分間に合います。SCCIPでは、その土台となる「考える力」「創造する力」「伝える力」を育てることを重視しています。
Q. アクティブラーニングって、ただ遊んでいるだけではないですか?
A. 「遊び」に見えるかもしれませんが、その中で子どもは高度な思考を巡らせています。埼玉大学との連携による科学的なカリキュラム設計により、「遊び」の中に明確な学習目標が組み込まれています。
まとめ:21世紀を生き抜く力は、レゴスクールで育つ
これからの時代、AIやテクノロジーがどれだけ発達しても、**「自分で考え、創造し、人と協力する力」**は、人間にしか持てない価値です。
レゴスクールの効果は、単なる知識やスキルの習得ではありません。
21世紀型スキルという「一生モノの力」を、アクティブラーニングという「最も効果的な学び方」で育てること。
それが、25年間SCCIPが追求してきた教育です。
お子さまの未来のために、今、できることを一緒に始めませんか?
【体験授業受付中】21世紀型の学びを、実際に体験してみませんか?
「アクティブラーニングってどんな感じ?」「うちの子に合うかな?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ体験授業にお越しください。
埼玉・東京・神奈川を中心に10教室以上を展開中
📍 お近くの教室を探す・体験授業のお申し込みはこちら
https://sccip-jp.com
※体験授業の料金や内容は教室によって異なります。詳しくは各教室ページをご確認ください。
子どもたちの「自ら学ぶ力」を、一緒に育てていきましょう。