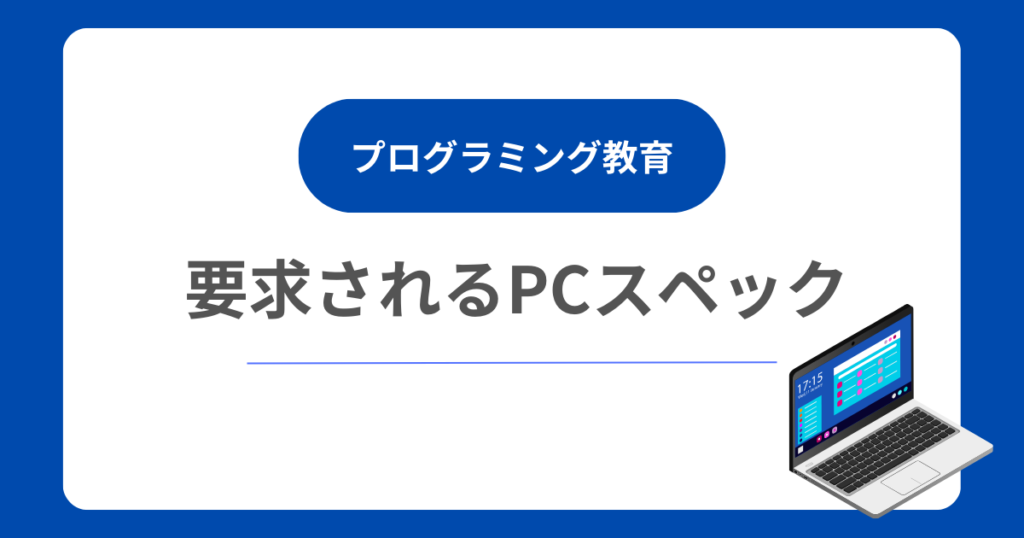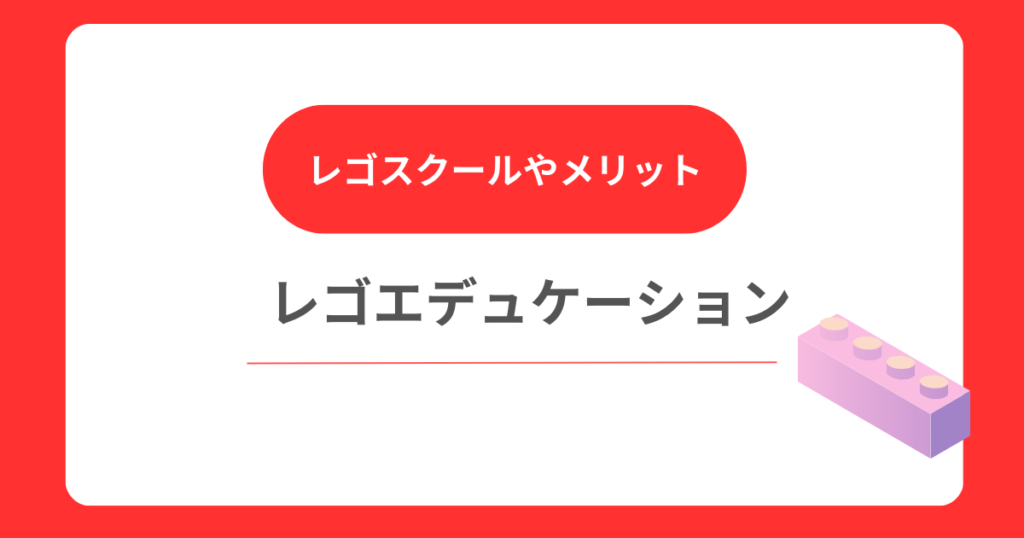People holding miniature figuresの写真 – Unsplashの人間の無料画像より引用
子どもが夢中になりながら学べる教材を探していると、「LEGO® SPIKE™(レゴ スパイク)」という名前をよく耳にしますよね。
レゴ SPIKEは、プログラミングとロボット工学を組み合わせた教育用キット。
ブロックを組み立てながら動きをプログラムできるので、遊びの延長でSTEAM(Science、 Technology、 Engineering、 Arts、 Mathematics)教育が実践できる優れものです。
そしてこのSPIKEを使うと、なんとあの「ピタゴラスイッチ」のような仕掛けを自分の手でつくることもできるんです!
今回は、レゴ SPIKEを活用したピタゴラスイッチづくりを通して、子どもがどんな力を育てられるのか、また家庭や学校での活用ポイントをご紹介します。
ピタゴラスイッチ×レゴ SPIKE:最高のSTEAM教材コラボ!

白い丸い皿にレゴブロックの写真より引用
ピタゴラスイッチといえば、ボールが転がり、ドミノが倒れ、風車が回って…と、まるで魔法のように次々と動く仕掛けが魅力ですよね。
この「一連の動き」を自動的に連鎖させる仕組みは、論理的思考力・空間認識力・創造力を育てる絶好の教材です。
レゴ SPIKEには、モーターやセンサー、プログラミング機能が備わっています。
つまり、ただの「仕掛け」ではなく、センサーで反応して動くピタゴラスイッチを作れるということです。
たとえば
- ボールがセンサーを通過したら、モーターが回ってドミノを押す
- 光センサーが明るさの変化を感知したら、アームが動く
- タッチセンサーを押すと、次の動作に連鎖して仕掛けが進む
このように、プログラムと物理的な動きを融合させることで、ただの「工作」から一歩進んだSTEAM体験が可能になります。
【レゴで自作】無限に動き続ける!「無限ビー玉マシン」の仕組みを徹底解説
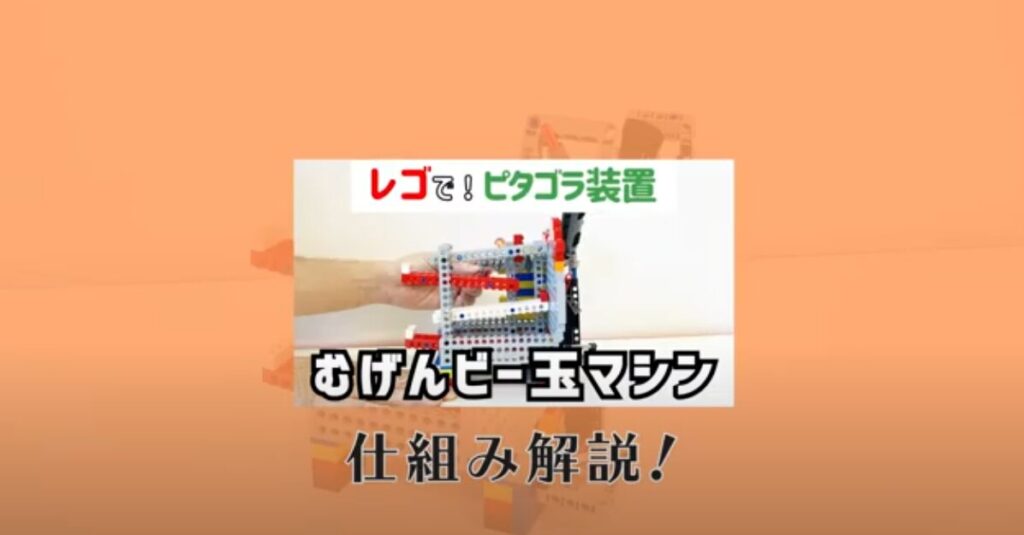
【レゴで!ピタゴラ装置】むげんビー玉マシン 解説動画 より引用
ブロックとロボットで学ぶ教室「エルプレイス」のYouTubeチャンネルにて、レゴブロックを用いたピタゴラ装置「無限ビー玉マシン」の詳細な解説動画が公開されています。
ビー玉が途切れることなく流れ続ける驚きのメカニズムを、スライダー部分と回転羽根部分の二つに分けてご紹介します。
「無限ビー玉マシン」とは

【レゴで!ピタゴラ装置】むげんビー玉マシン 解説動画 より引用
この装置は、ビー玉をスタート地点に置くと、スライダーを転がり落ち、回転する羽根に持ち上げられ、再び上のスライダーへと送られるという一連の動作を、永遠に繰り返すように設計されています。
装置は、レゴのテクニック系のパーツを中心に構成されており、主に以下の二つの機構で成り立っています。
- スライダー部分(ビー玉が転がり落ちる経路)
- 回転する羽根の部分(ビー玉を上へ持ち上げる機構)
1. スライダー部分の仕組みと工夫

【レゴで!ピタゴラ装置】むげんビー玉マシン 解説動画 より引用
スライダー部分は、穴の開いたパーツ「ビーム」を斜めに配置して作られています。
- 角度と速度
スライダーの傾斜角度を急にするとビー玉は速く転がりますが、勢いがつきすぎて飛び出す可能性が高まるため、受け止め部分(次の羽根の部分)を調整する必要がある点に注意が必要です。 - 構造
スライダーの部品と部品の間には、青い「ロングペグ」などを使って約1ポッチ分の隙間を作り、ビー玉がスムーズに転がるように設計されています。 - ストッパー:
ビー玉が羽根の部分に正しく誘導されるよう、終点にはストッパーが取り付けられています。 - 拡張性
スライダーは現在の段数にとどまらず、ビームを増やせばさらに多くの段や、より長い経路を作ることも可能です。
2. ビー玉を運び上げる回転羽根のメカニズム

【レゴで!ピタゴラ装置】むげんビー玉マシン 解説動画 より引用
無限装置の核となるのが、ビー玉を上の段へと運び上げる3枚の羽根を持つ回転機構です。
- ギア比の秘密
この機構は、ハンドル操作の力を効率的に伝達するために歯車(ギア)が使われています。
特に重要なのは、ギア比です。ハンドル側の歯車(8枚刃)と、羽根の軸に接続された歯車(24枚刃)が組み合わされており、その比率は8対24、すなわち1対3になっています。 - 正確な動作:
この1対3のギア比により、ハンドルを一周させると、羽根はちょうど3分の1だけ回転します。
羽根が3枚あるため、ハンドルを操作するたびに次の羽根が適切な位置に移動し、上のスライダーから転がり落ちてきたビー玉を確実に受け止められるようになっています。 - 誘導壁
持ち上げられたビー玉は、羽根の回転と同時に取り付けられた大きな壁に沿ってスライドし、元のスライダーの経路へと誘導されます。
この壁は、ビー玉が横にこぼれるのを防ぐストッパーの役割も果たしています。
本動画は、レゴのテクニックパーツを用いた機械的な構造や、ギア比の計算といった工学的な要素を視覚的に学ぶことができるため、自作ピタゴラ装置に挑戦したい方にとって非常に参考になります。
子どもが学べる3つのSTEAMスキル

4体のレゴ ミニフィギュアのセレクティブフォーカス撮影の写真 – Unsplashの間の無料画像より引用
SPIKEでピタゴラスイッチを作る過程では、次のようなスキルが自然と身につきます。
① 論理的思考力
「もしボールが通ったらモーターを回す」というように、“条件→結果”を考える思考が育ちます。
これはプログラミングの基本であり、将来的に数学や理科の理解にもつながります。
② 問題解決力
仕掛けがうまく動かない時、子どもたちは試行錯誤を繰り返します。
どこが原因なのかを探り改善する力、つまり問題解決力を養えます。
成功した瞬間の「できた!」という達成感は、次のチャレンジへのモチベーションにもなります。
③ チームワークと創造力
友だちや家族と一緒に作ると、「ここはどうつなげよう?」「この動きが面白いかも!」と意見を出し合うことで、協働的な創造が生まれコミュニケーション力もアップします。
教育現場でも注目されるSPIKEの活用

背景パターンの写真 – Unsplashのテクスチャーの無料画像より引用
文部科学省が推進するプログラミング教育の必修化により、学校でもSPIKEのようなロボティクス教材が導入されています。
特にピタゴラスイッチ的な活動は、
- 自由研究や探究活動のテーマ
- クラブ活動・STEMイベントの展示作品
- 理科・算数・図工の横断的授業
として活用しやすく、「楽しみながら学ぶ」アクティブラーニングの代表例となっています。
SPIKEは小学生向けの「SPIKE Essential」と、中高生向けの「SPIKE Prime」の2種類があります。
ピタゴラスイッチのような仕掛け作りなら、まずはEssentialでも十分でしょう。
Primeでは、より複雑な動作や長い連鎖をプログラムでき、物理や工学の理解もさらに深められます。
家庭でも気軽にできる!親子で楽しむピタゴラスイッチ学習

子供がレゴの箱で遊んでいるより引用
SPIKEは学校だけでなく、家庭学習にも最適です。
親子で一緒に作ることで、子どもの創造性を引き出し、家族の会話も自然と増えます。
たとえば以下の様な遊びを親子で楽しむことができるでしょう。
- 「今日は風の力だけで動かす仕掛けを作ってみよう!」
- 「5つの動きを連鎖させたらクリア!」
ゲーム感覚で取り組むと、子どもは夢中になります。
完成したらスマホで動画を撮って“自作ピタゴラスイッチ”を記録するのもおすすめです。
自分のアイデアが形になり、動く瞬間は感動ものです。
SPIKEで“考える力”を育てよう

赤、緑、青のレゴブロックの写真 – Unsplashのキッズの無料画像より
レゴ SPIKEでピタゴラスイッチを作る体験は、単なる工作やプログラミングの練習にとどまりません。
「どうすれば思い通りに動くか?」を考え、試行錯誤しながら形にしていく過程そのものが、STEAM教育の本質です。
センサー・モーター・プログラムを自由に組み合わせれば、子どもの発想力は無限に広がります。
「遊びながら学ぶ」ことを実現してくれるレゴ SPIKEは、まさに次世代の学びのパートナー。
家庭でも学校でも、ぜひSPIKEを使ってピタゴラスイッチづくりに挑戦してみてください。
きっと、子どもの“考える力”と“つくる楽しさ”が花開くはずです。