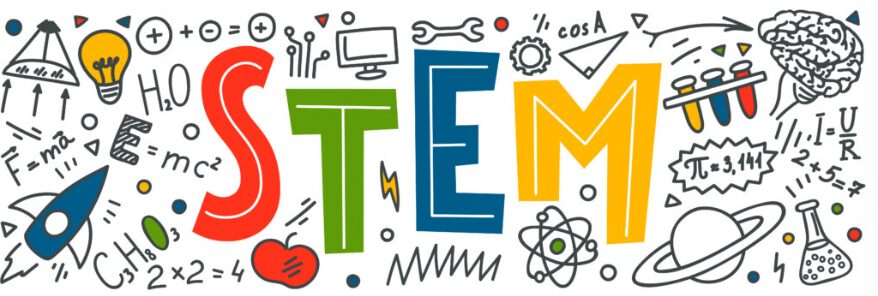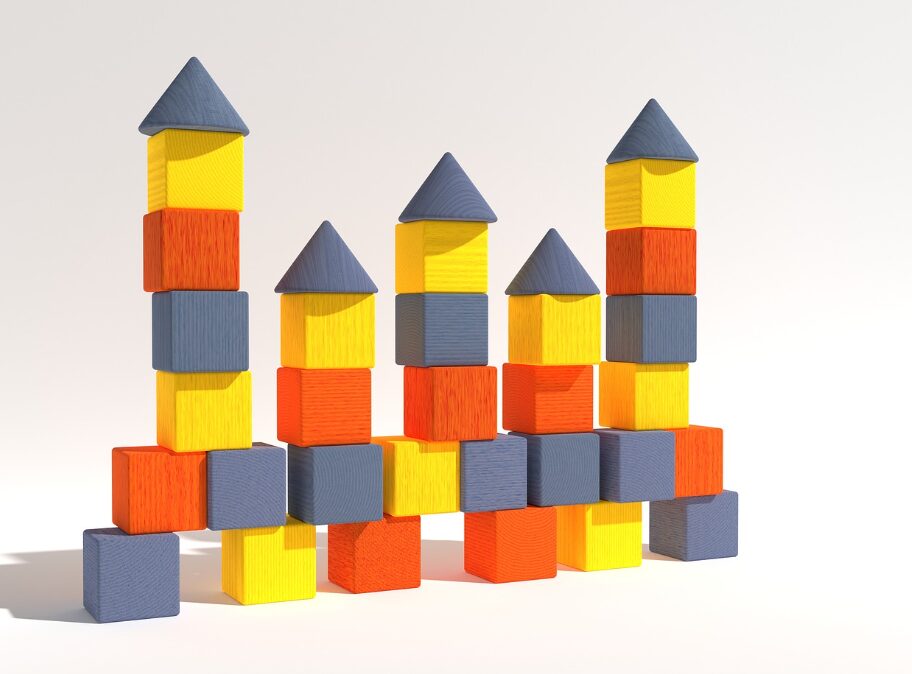木更津・袖ヶ浦でもプログラミングが習える!地域密着型TopSystemで始める子どものSTEM教育
木更津・袖ヶ浦エリアにもついに本格的なプログラミング教室が登場
「プログラミング教室って都市部にしかないんでしょ?」「木更津や袖ヶ浦でも質の高いプログラミング教育を受けられるの?」
そんな風に思っていませんか?実は、木更津・袖ヶ浦エリアでも、都市部に負けない本格的なプログラミング教育を受けることができるんです。
TopSystemプログラミング教室なら、袖ヶ浦を拠点に、木更津エリアからも通いやすい立地で、25年の実績を持つ本格的なレゴプログラミング教育を提供しています。もう東京や千葉市まで遠距離通学する必要はありません!
木更津・袖ヶ浦エリアの教育環境が変わっている
プログラミング教育への関心の高まり
2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されて以来、木更津・袖ヶ浦エリアでも保護者の間でプログラミング教育への関心が急速に高まっています。
地域の保護者の声
- 「学校の授業だけで大丈夫?」
- 「うちの子、プログラミングについていけてるのかな?」
- 「将来のために何かさせてあげたいけど、近くに良い教室がない…」
こうした不安を抱える保護者が増える中、TopSystemは地域に根ざした質の高いプログラミング教育を提供しています。
地方でも都市部と同レベルの教育が可能
「地方だから教育の選択肢が少ない」という時代は終わりました。TopSystemでは、都市部の大手教室と同等、いえそれ以上の教育クオリティを提供しています。
TopSystemの強み
- 日本初のレゴ教育導入の実績(2000年〜)
- 埼玉大学STEM教育研究センターとの連携
- 全世界3万人の受講実績
- 地域密着型のきめ細かい指導
なぜレゴを使ったプログラミング教育なのか?
子どもにとって親しみやすい教材
木更津・袖ヶ浦エリアのお子さまの多くも、レゴブロックで遊んだ経験があるのではないでしょうか。TopSystemでは、この馴染み深いレゴを教材として活用することで、プログラミング学習への心理的ハードルを大きく下げています。
「プログラミングは難しい」という先入観を持つことなく、「レゴで遊びながら学ぶ」という感覚で自然と学習に取り組めるのです。
実体験による深い理解
多くのプログラミング教室が画面上での学習に留まる中、TopSystemでは実際に手を動かしてロボットを組み立て、それをプログラミングで動かすという体験型学習を重視しています。
体験型学習の効果
- プログラミングの結果を目で確認できる
- 成功・失敗の体験から学ぶ問題解決力
- 物理的な操作による深い理解
- 達成感による学習継続意欲の向上
TopSystemで学べる充実のコース内容
WeDoクラス(低学年向け)
対象年齢:年長〜小学3年生
使用教材:LEGO WeDo
学習内容:
- 基本的なロボット製作
- 簡単なプログラミング操作
- 色や形の認識
- 基本的な動きの理解
効果:プログラミング的思考の基礎を楽しみながら身につけることができます。
ロボティクスクラス(高学年向け)
対象年齢:小学4年生〜中学生
使用教材:LEGO EV3
学習内容:
- 高度なロボット製作
- センサーを使った制御
- 複雑なプログラミング
- チームでの問題解決
効果:論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション力を総合的に育成します。
イチゴジャムクラス
対象年齢:小学生〜中学生
学習内容:
- 手のひらサイズのパソコン組み立て
- BASICプログラミング
- 電子工作の基礎
- コンピューターの仕組み理解
効果:より深いコンピューター理解と電子工作の基礎を身につけます。
木更津・袖ヶ浦エリアの保護者が実感する変化
学習面での成長
木更津市在住 Aさん(小学3年生の保護者) 「最初は遊びの延長かと思っていましたが、息子が家でも物事を順序立てて説明するようになりました。学校の先生からも『論理的に考える力がついてきましたね』と言われて驚いています」
袖ヶ浦市在住 Bさん(小学5年生の保護者) 「算数の図形問題が得意になりました。立体的に物事を考える力がついたようで、成績も向上しています。レゴで培った空間認識能力が活かされているんだと思います」
性格面での変化
木更津市在住 Cさん(小学4年生の保護者) 「内気だった娘が、教室でのプレゼンテーションを通じて自分の考えを積極的に発表するようになりました。将来への自信につながっています」
袖ヶ浦市在住 Dさん(小学6年生の保護者) 「失敗を恐れてチャレンジしたがらなかった息子が、『失敗してもやり直せばいい』という考え方になりました。粘り強く取り組む姿勢が身につきました」
地域密着だからこそのメリット
アクセスの良さ
通いやすい立地
- 袖ヶ浦市内に拠点
- 木更津市内からも車で約15〜20分
- 十分な駐車場完備
- 送迎の負担を軽減
地域に根ざした指導
地元の教育事情を熟知
- 木更津・袖ヶ浦の小学校事情を理解
- 地域の子どもたちの特性に合わせた指導
- 学校のプログラミング教育との連携
- 地域の保護者ニーズへの対応
柔軟な対応
大手チェーン教室では難しい、個別のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
具体例
- 学校行事に合わせたスケジュール調整
- 個々の学習ペースに応じた指導
- 保護者との密な連携
- 地域の特性を活かした学習内容
充実した学習環境と時間割
通いやすい時間設定
平日(火〜金曜日)
- 16:00〜17:00
- 17:20〜18:20
- 18:40〜19:40
- 20:00〜21:00
土曜日
- 10:30〜11:30
- 13:00〜14:00
- 15:00〜16:00
- 17:00〜18:00
学校の下校時間や他の習い事との両立を考慮した豊富な時間選択肢を用意しています。
安心・安全な学習空間
- 清潔で明るい教室環境
- 少人数制による丁寧な指導
- 安全性を重視した教材管理
- 保護者の見学も歓迎
適正価格で質の高い教育
透明性のある料金体系
入学金:10,000円(税別)
月謝(税別)
- WeDoクラス:13,000円(月4回)
- ロボティクスクラス:14,000円(月4回)
- イチゴジャムクラス:6,000円(月3回)
コストパフォーマンスの高さ
他の習い事との比較
- 一般的な学習塾:月5,000円〜19,500円(教科学習のみ)
- 英会話教室:月8,000円〜15,000円(英語のみ)
- TopSystem:月6,000円〜14,000円(STEM教育の総合スキル)
21世紀型スキルを総合的に育成できることを考慮すると、非常にコストパフォーマンスの高い投資といえます。
将来への確実な投資
2025年大学入試改革への対応
2025年から大学入学共通テストに「情報」科目が導入されることをご存知ですか?プログラミング的思考力が直接評価される時代が来ています。
TopSystemで身につくスキル
- 論理的思考力
- 問題解決能力
- アルゴリズム的思考
- 情報技術への理解
AI時代を生き抜く力
これからの時代、文系・理系を問わずプログラミング的思考力は必須のスキルです。早期からの学習経験は、お子さまの将来の選択肢を大きく広げます。
体験教室で実際の効果を確認
TopSystemでは随時無料体験教室を開催しています。木更津・袖ヶ浦エリアからも多くのご家族にお越しいただいています。
体験内容
- レゴロボット製作体験(45分)
- 実際のレゴ教材を使用
- 基本的な組み立て体験
- プログラミング操作体験(30分)
- 簡単な動作プログラムの作成
- ロボットの実際の動作確認
- 保護者向け説明会(15分)
- カリキュラムの詳細説明
- 教育効果についての解説
- 質疑応答
体験参加者の声
木更津市在住の保護者 「木更津にもこんな本格的な教室があるなんて知りませんでした。都市部まで通わせることを考えていましたが、これなら安心して通わせられます」
袖ヶ浦市在住の保護者 「体験で子どもが目を輝かせて取り組む姿を見て、これが本当のプログラミング教育だと実感しました。即座に入会を決めました」
まとめ:木更津・袖ヶ浦で始める新しい学び
木更津・袖ヶ浦エリアでも、都市部に負けない質の高いプログラミング教育を受けることができる時代になりました。
TopSystemを選ぶ理由
- 地域密着:木更津・袖ヶ浦エリアに根ざした教育
- 実績と信頼:25年の歴史を持つ確かなカリキュラム
- 体験型学習:レゴを使った楽しく深い学び
- 通いやすさ:アクセス良好で柔軟な時間設定
- 適正価格:質の高い教育を無理のない費用で
- 将来性:AI時代に必要なスキルの総合育成
「うちの地域にはいい教室がない」という時代は終わりました。お子さまの可能性を最大限に引き出す教育が、すぐ近くで受けられます。
今すぐ始められます 👉 TopSystemプログラミング教室の詳細・体験申込みはこちら
木更津・袖ヶ浦エリアのお子さまたちの輝かしい未来を、TopSystemと一緒に築いていきませんか?まずは無料体験教室で、レゴプログラミングの魅力を実際に体感してください!
木更津・袖ヶ浦でもプログラミングが習える!地域密着型TopSystemで始める子どものSTEM教育 Read More »