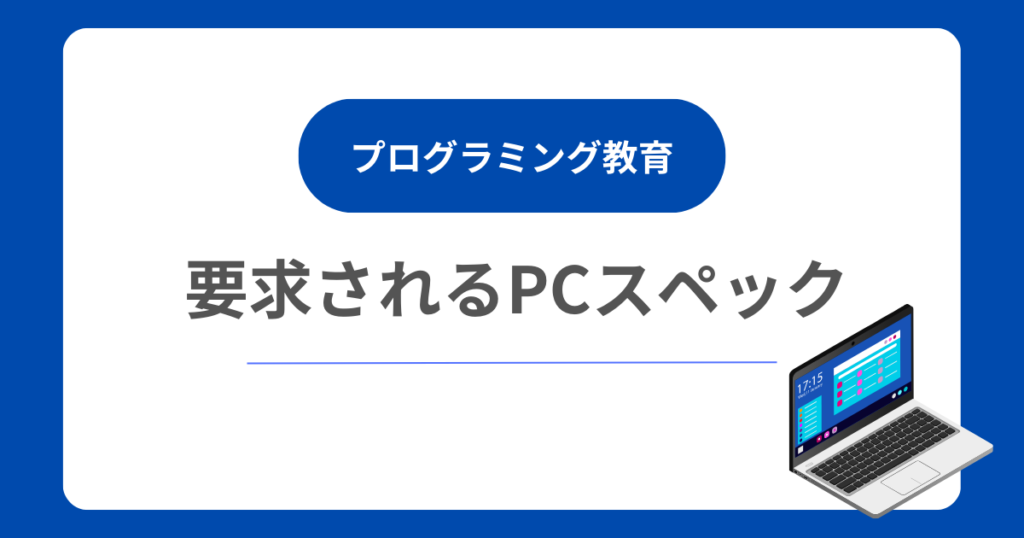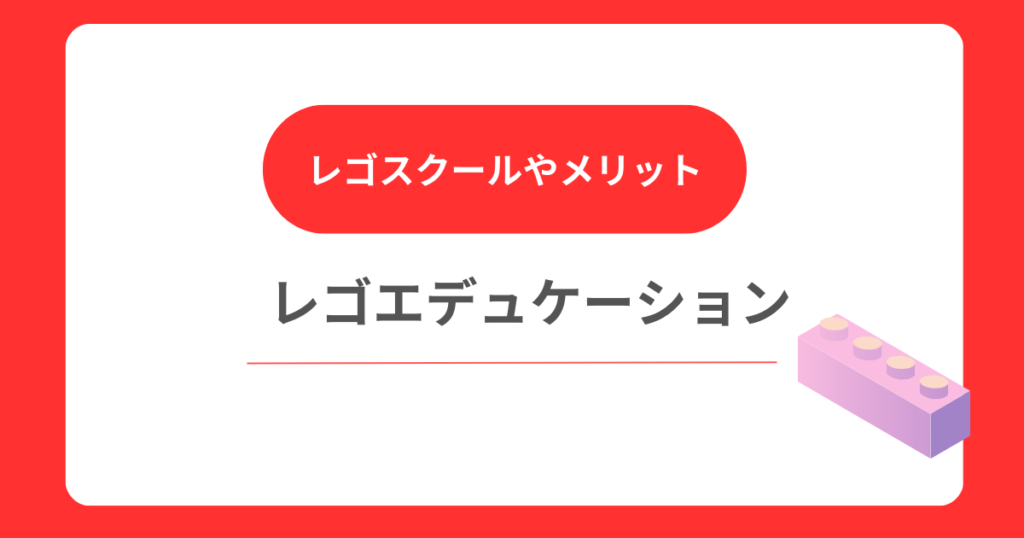【概要】
国内ではSTEM教育の重要性が高まる中、各地域で先進的な実践事例が展開されています。
本記事では、「兵庫県教育委員会」「加古川東高等学校」「高知県立山田高等学校」についての取り組みを詳しく紹介します。
国内におけるSTEM教育の実践事例について

以下では国内におけるSTEM教育の実践事例について紹介します。
【兵庫県教育委員会の事例】英語を含めた国際的な文理融合型教育を実践
兵庫県教育委員会が主導した2020年から2022年までの教育改革では、県立高等学校3校をSTEAM教育実践モデル校として指定し、未来を見据えた文理融合型カリキュラムの開発とSTEAM学科の設置を積極的に推進してきました。
従来のSTEAM教育(科学、技術、工学、芸術、数学)に英語(English)の要素を加えることで、国際社会で活躍できる人材育成を目指す先進的な取り組みが展開されました。
カリキュラム全体を通して課題解決型の探究活動が体系的に位置づけられており、英語を母語とする教員を特別に採用・配置することにより、英語を活用した理系分野の深い課題研究が可能となりました。
各モデル校には最新技術を体験できるSTEAM ROOMが整備され、3Dプリンタやドローンをはじめとする先端ICT機器が導入されたことで、生徒たちは実践的な学びの環境で創造力を発揮できるようになりました。
教育現場での具体的な実践例として、「数学×スポーツ」では数学的分析によるパフォーマンス向上研究、「音楽×プログラミング」では技術とアートの融合による新たな表現方法の開発、「歴史×データサイエンス」では過去の事象をデータ科学的手法で分析するなど、従来の教科の枠を超えた多彩な授業が展開されました。
モデル校における先進的な取り組みは、未来社会を創造的に生きるために必要な複合的思考力と問題解決能力を育成するという、新時代の教育モデルの確立に向けた重要な一歩となっています。
【兵庫県立加古川東高等学校の事例】プロジェクト型の探究活動を展開
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校として知られる兵庫県立加古川東高等学校では、未来社会を創造的に生きる人材の育成を目指し、明確な生徒像と育成すべき能力を設定した上で、学校全体をあげてSTEAM教育を組織的かつ体系的に推進しています。
教育改革の中核を担うのは11名の教員で構成される教育企画部であり、従来の教科の枠組みを超えた横断的なカリキュラム開発と実践に取り組んでいます。
STEAM教育推進の専門担当者として数学・理科教員が任命され、多様な特別講座の企画・運営を通じて先進的な教育活動を展開しています。
特別講座においては、ビッグデータを活用した地域社会の課題発見・解決プロジェクトやドローン技術による物流革新シミュレーションなど、実社会と直結した複合的な探究活動が実施されています。
加古川東高等学校の取り組みで特筆すべき点は、理数系科目にとどまらず国語や地理歴史といった人文社会科学分野も含めた全教科においてSTEAM教育の理念を取り入れている先進性にあります。
文系科目においても科学的思考やデータ分析の手法を導入することで、生徒たちは多角的な視点から問題を考察する力を養うことができます。
教科の枠を超えたプロジェクト型学習を通じて、生徒たちは知識の統合と創造的応用の経験を積み重ね、現代社会が直面する複雑な課題に対応できる思考力と実践力を身につけています。
加古川東高等学校における全校的なSTEAM教育の実践は、文理融合型の新しい学びのモデルとして、今後の高校教育改革における重要な参考事例となることが期待されています。
【高知県立山田高等学校の事例】自ら探究活動を深める姿勢を育成
高知県立山田高等学校では、現代社会の複雑な課題に立ち向かうための教育改革として「グローバル探究科」を独自に設立し、明確な解答が容易に見いだせない問いに対して粘り強く探究できる生徒の育成に取り組んでいます。
山田高等学校の教育プログラムの優れた特徴は、3年間を通じて系統的・段階的に探究力を養成するカリキュラム設計にあり、各学年に明確な到達目標を設定することで確実な成長を促しています。
1年次のカリキュラムでは、探究活動の基礎となる「型」の習得を目指し、課題の発見・情報収集・データ分析・結論導出・プレゼンテーションなどのプロセスを、グループワークを通じて体験的に学習します。
チームでの協働作業を重視することで、多様な視点を尊重しながら問題解決に取り組む姿勢も同時に育まれています。
2年次に進むと、1年次で身につけた探究の基本的スキルを土台として、個人での研究活動へと移行します。
他の生徒や教員との意見交換を積極的に行いながらも、自分自身のテーマと向き合い、より深い考察と独自の視点の確立を目指す段階へと発展させます。
最終学年となる3年次では、大学での専門的な学術研究を見据え、より高度な分析手法や理論的枠組みを用いた探究活動に挑戦し、研究論文の執筆という具体的な成果物の完成を目標としています。
グループでのポスター発表から始まり、最終的には個人による本格的な論文作成へと段階的に発展させることで、主体的に課題を設定し、深い学びを追求できる人材を育成する先進的な教育モデルが確立されています。
株式会社 SCCIP JAPAN(スキップ ジャパン)について
SCCIP JAPANは、レゴ®ブロックを活用したSTEM教育のパイオニアとして、2000年に日本初のレゴを使った民間教育教室を開設しました。
以来、幼児から小学生を対象に、創造力・論理的思考力・問題解決力を育む「ものづくり教育」を国内外で提供し続けています。
ご家庭・保護者の方へ
SCCIPの教室では、子どもたちがレゴ®ブロックやロボット教材を使って、試行錯誤しながら自分のアイデアを形にしていきます。
ただ遊ぶのではなく、「つくる楽しさ」を通じて学ぶ力を自然に育てる——それがSCCIPのものづくり教育です。
▶ 全国の教室紹介はこちら:
👉 https://sccip-jp.com/classroom-list/
教育事業者・導入を検討される方へ
SCCIP JAPANでは、STEM教育やプログラミング教育を導入したい学習塾・保育園・学童保育・教育施設向けに、
研修・教材・運営ノウハウを一括提供するメンバーシップ制度(加盟店・フランチャイズ)をご用意しています。
カリキュラムは埼玉大学STEM教育研究センターとの連携により開発されており、
現在、国内10教室以上、海外(インド・スリランカ・タイ・アメリカ)でも直営教室を展開。
導入後も継続的な運営支援を行い、教育の質と安定を両立させます。
▶ 加盟・導入のご相談はこちらからお問い合わせください。
👉 https://sccip-jp.com/contact/
お問い合わせ・会社情報
株式会社 SCCIP JAPAN(スキップ ジャパン)
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-17-15 ヨシダFGビル
担当: 勝村
TEL: 03-6256-9406
MAIL: info@sccip-jp.com
📩 お問い合わせページ:
👉 https://sccip-jp.com/co